はじめに
介護人材の不足が深刻化するなか、日本では外国人介護人材の受け入れが年々増加しています。
EPA(経済連携協定)による来日、技能実習制度、特定技能制度など複数のルートがあり、すでに多くの外国人が介護の現場で活躍しています。
この記事では、現場で外国人スタッフと共に働いてきた介護職歴20年以上の視点から、外国人介護人材の現状と課題を解説します。
1.外国人介護人材が増えている背景

・日本の高齢化による介護人材不足
・若い日本人の介護職離れ
・EPAや特定技能制度の整備により来日がしやすくなった
👉 人材不足については、詳しくはこちらの記事を → 『介護職の離職率とその背景:現場で見えてくる課題と改善策』
2.外国人介護人材の主な受け入れ制度
EPA介護福祉士候補者制度
→ フィリピン・インドネシア・ベトナムなどの協定国から受け入れ
技能実習制度
→ 介護の現場で実務を通じて技術を学びながら就労
特定技能制度(介護分野)
→ 日本語能力試験N4以上と介護技能評価試験に合格すれば就労可能
3.現場で感じるメリット
積極的で明るく、コミュニケーションが得意な人が多い
若い世代が多く体力面でも貢献
多文化交流による職場の雰囲気向上
4.現場での課題
日本語の壁
→ 医療・介護用語の習得に時間がかかる
文化・習慣の違い
→ 食事介助や入浴習慣などで戸惑いがある
長期就労の難しさ
→ 技能実習は最長5年、キャリアを継続できず帰国する例も
👉 コミュニケーションについては、詳しくはこちら → 『高齢者とのコミュニケーションのコツ5選』
5.受け入れを成功させるために必要なこと
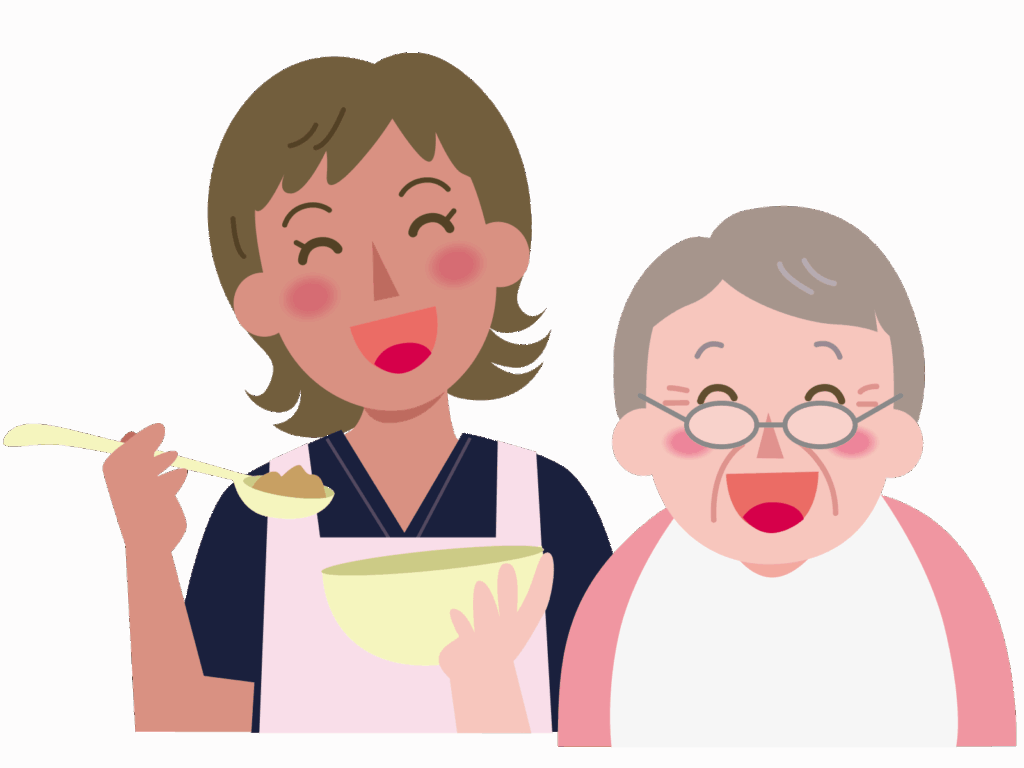
現場スタッフ全員が多文化理解を持つ研修の実施
わかりやすい日本語マニュアルの整備
生活面でのサポート体制(住居・相談窓口など)
資格取得支援とキャリアパスの明確化
6.現場の声
40代・施設長
「人手不足の中で、外国人スタッフは本当に助かっています。言語や文化の壁はありますが、サポート体制を整えれば定着率は上がると感じています。」
20代・外国人介護士
「最初は敬語や専門用語が難しかったけれど、利用者さんが笑顔で応えてくれたことで自信がつきました。」
まとめ
外国人介護人材は、現場の人手不足を補い、多様性をもたらす重要な存在。
言語・文化の壁や制度の制限など課題も多いが、受け入れ体制次第で力を発揮できる。
今後は、生活・教育支援とキャリアパスの整備が鍵となる。



コメント