はじめに
介護の現場で最も多いトラブルの一つが「転倒」や「誤嚥」などの事故です。
これらは一瞬の油断から起こることも多く、スタッフ一人ひとりの観察力と工夫が重要になります。
この記事では、20年以上の介護現場経験を持つ筆者が、高齢者の事故を防ぐためのリスク管理と実践的なポイントを解説します。
1.高齢者に多い事故の種類
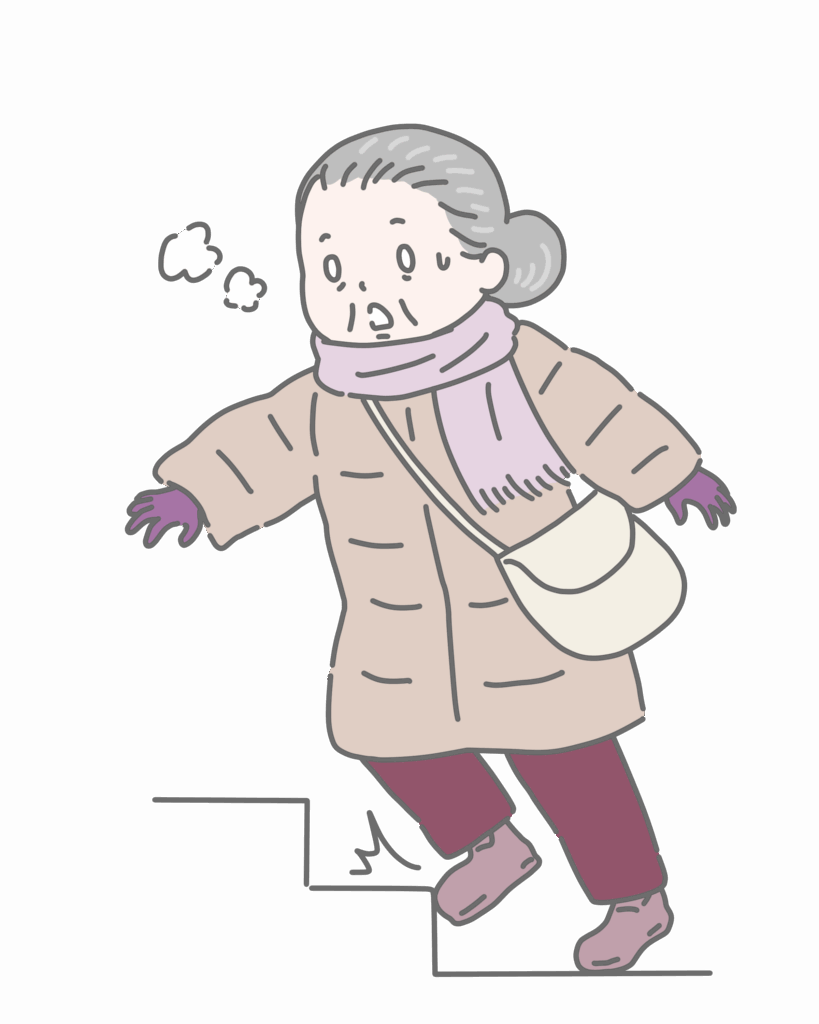
転倒・転落事故
→ ベッド・トイレ・入浴中などで起きやすい
👉 転倒の8割は“日常動作中”に発生します。普段の動きこそ要注意。
誤嚥・窒息事故
→ 食事中・服薬時に多い
👉 “急がせない”“姿勢を整える”が安全の基本。
やけど・熱傷事故
→ 入浴時や暖房器具の使用時に発生
👉 “手を添える・温度を測る”たった一手間が命を守ります。
徘徊・行方不明事故
→ 認知症の進行によるものが多い
👉 “外に出る”=“危険”ではなく“目的がある行動”と理解することが第一歩。
2.事故を防ぐための環境づくり
① 物理的な安全確保
手すりの設置、高さ調整
滑り止めマット、段差の解消
ベッドの高さを低くする
👉 “安全な環境”とは、介助がなくても自立して動ける環境のこと。
② 動線の見直し
よく使う場所(トイレ・水分コーナー)への導線を確保
通路の照明を明るく
👉 “夜間の一歩”が事故を防ぎます。照明と導線の工夫がリスクを半減。
3.スタッフの観察と記録の重要性
「いつ・どこで・どんな動きで」つまずきやすいかを記録
転倒予兆(ふらつき・着座の不安定など)を共有
👉 事故は“偶然”ではなく“予兆の積み重ね”です。
詳しくは → 『デイサービスの1日を仕事目線で解説!介護士のリアルな役割』
4.転倒予防に役立つ運動と工夫
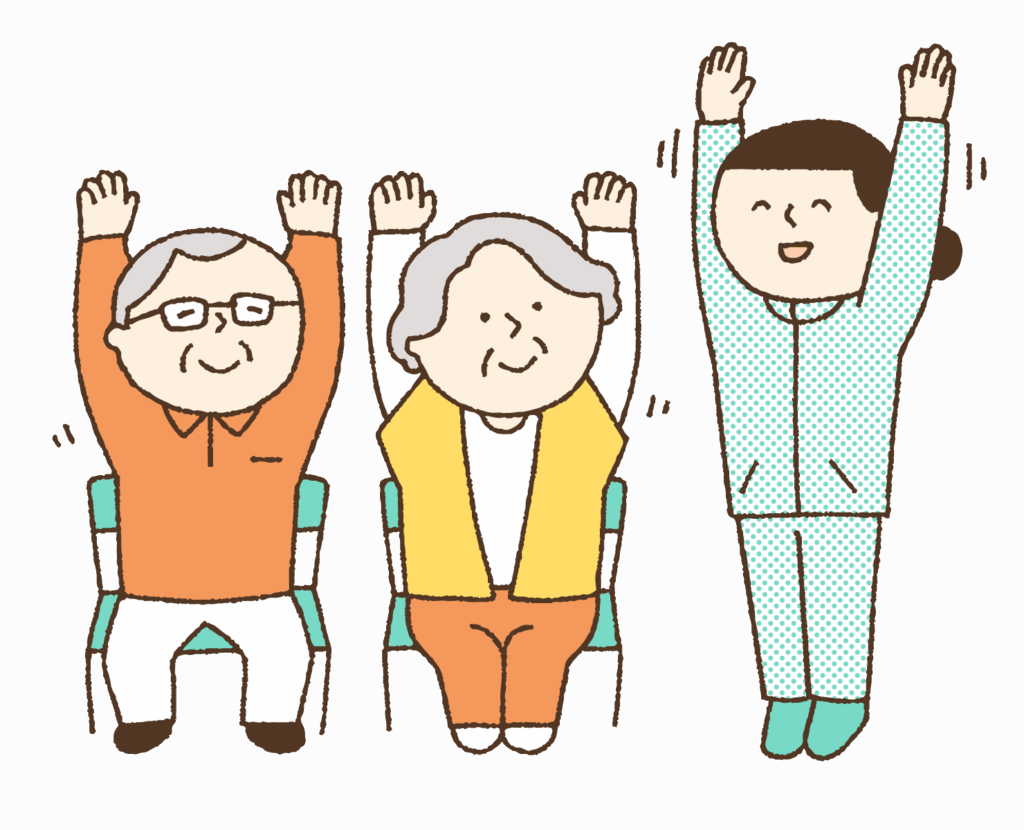
下肢筋力トレーニング(かかと上げ・片足立ち)
歩行補助具(杖・歩行器)の正しい使い方を指導
定期的な体力測定で変化を把握
👉 “動かないほうが安全”ではなく、“動ける体を作る”のが本当の事故予防。
5.ヒヤリ・ハット報告の活用
事故未遂も必ず共有し、再発防止策を検討
責任追及ではなく“チームの学び”として扱う
月1回の振り返りミーティングを実施
👉 「ヒヤリ」を共有できるチームは事故を防ぐチーム。
詳しくは → 『介護現場での新人がつまずきやすいポイントと解決法』
6.家族との連携もリスク管理の一部
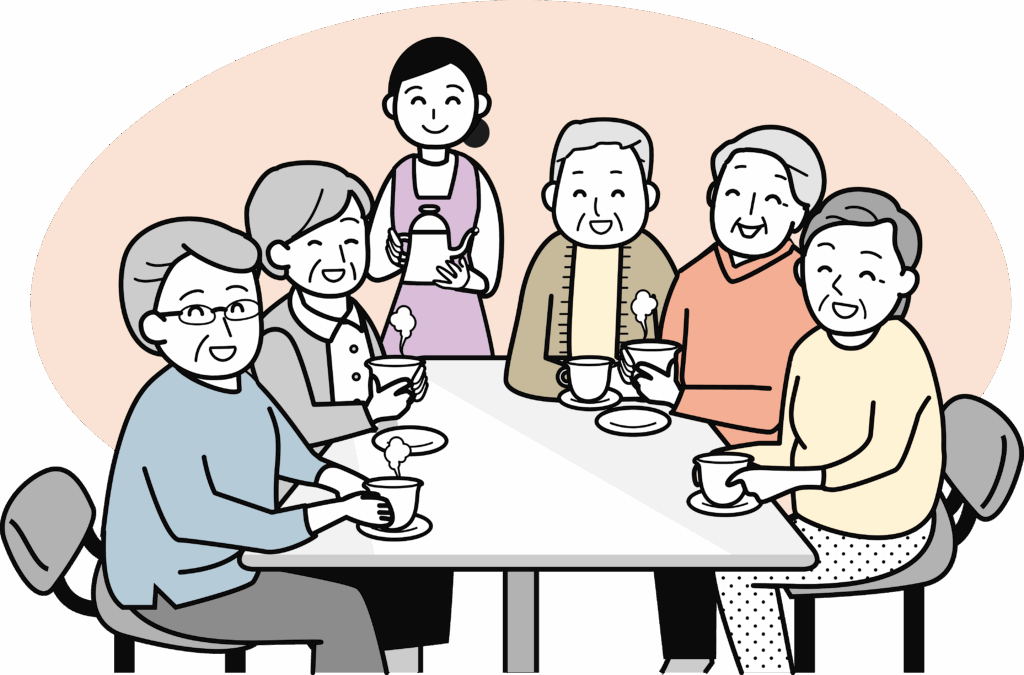
家族に「自宅での注意点」を共有
転倒・誤嚥のリスクを家庭内でも意識してもらう
状況の変化は早めに連絡・相談
👉 “家族もチームの一員”という意識を持つことが事故防止につながります。
7.現場の声
50代・介護福祉士
「転倒の多い方は“いつも同じタイミング”で起きることが多い。データを見返すとヒントが見えてきます。」
40代・施設長
「ヒヤリ報告を“叱らない文化”に変えてから、事故件数が減りました。」
まとめ
転倒・誤嚥・やけどなど、事故は“日常の中”に潜んでいる
環境整備・観察・運動・共有がリスク管理の柱
“チームで防ぐ”意識が現場を守る最大の力になる

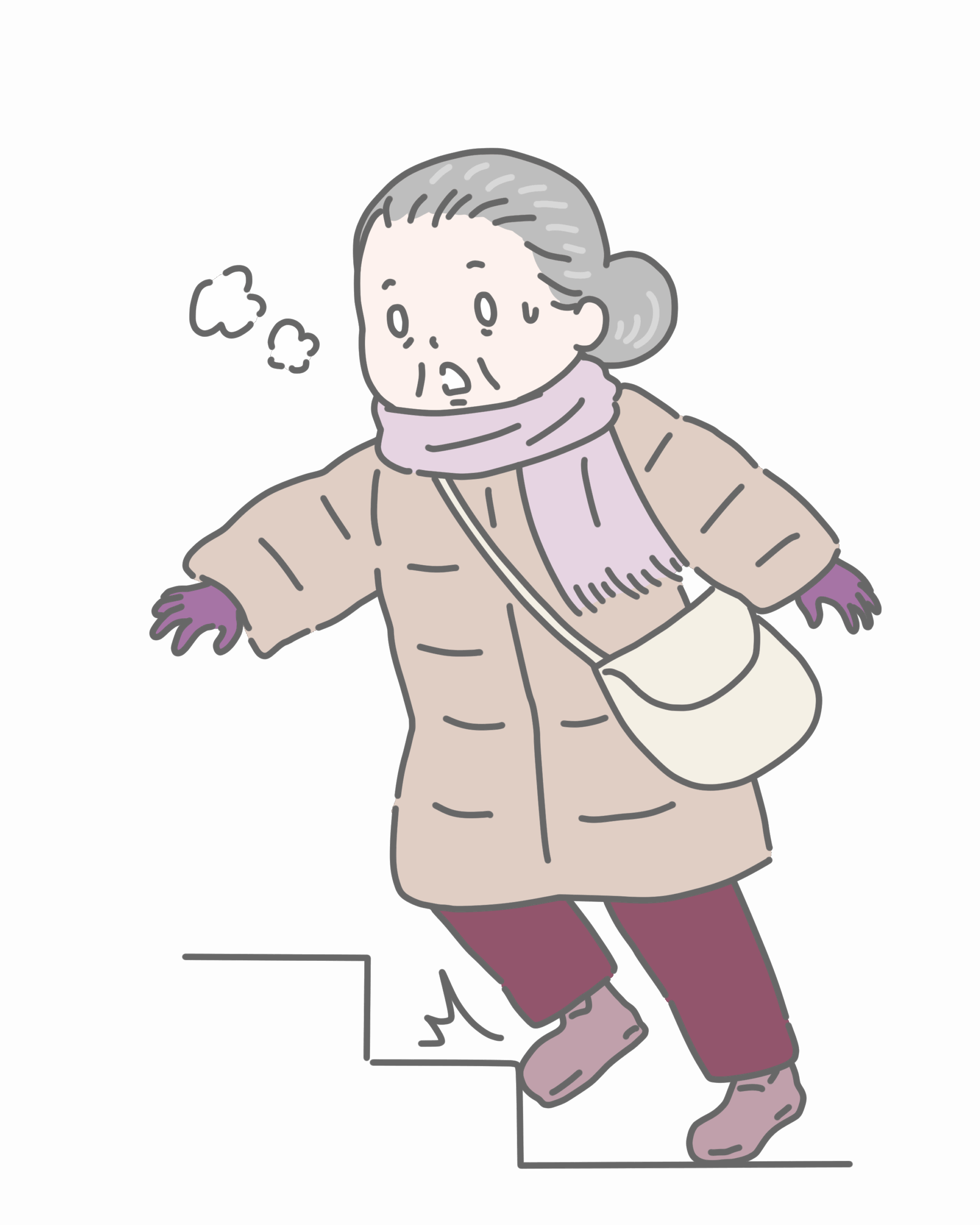

コメント